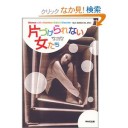「人間関係リセット」について。検索してざっと目を通してみた。
わたしくらいの歳になると、そこまで思い切ったことするのかなり不利っていうか、それ以上の新しい関係作って行くのってどんどん難しくなるらしい。リセットするなら若いうちに限る(極論すみません)って感じに受け取った。これいちばんなるほど!って思えた。
みんな疲れるんだ。疲れないような対策も書いてあって、思った通りわたしは真逆を行ってた。今がいちばん(気持ち)自由だな。でもいろいろごめんなさいってどうしてもちらっと思ってしまいます。これクセなんでしょうね、もう。
自分がリセットされないためには「必要な人」になること、だって。自分にしかないものを磨くこと。打算と妥協の関係は必ずしも悪くない(大筋)。
…もう挫けた。笑 そんなんむりー。必要ないけど、いても別にいいよ、くらいが関の山だから。いてもいいよ、と許されればいい。望み過ぎないように。わたしだって結局何も返せない。
おやすみなさい。明日いい日でありますように。
わたしくらいの歳になると、そこまで思い切ったことするのかなり不利っていうか、それ以上の新しい関係作って行くのってどんどん難しくなるらしい。リセットするなら若いうちに限る(極論すみません)って感じに受け取った。これいちばんなるほど!って思えた。
みんな疲れるんだ。疲れないような対策も書いてあって、思った通りわたしは真逆を行ってた。今がいちばん(気持ち)自由だな。でもいろいろごめんなさいってどうしてもちらっと思ってしまいます。これクセなんでしょうね、もう。
自分がリセットされないためには「必要な人」になること、だって。自分にしかないものを磨くこと。打算と妥協の関係は必ずしも悪くない(大筋)。
…もう挫けた。笑 そんなんむりー。必要ないけど、いても別にいいよ、くらいが関の山だから。いてもいいよ、と許されればいい。望み過ぎないように。わたしだって結局何も返せない。
おやすみなさい。明日いい日でありますように。
以前、もう10年くらい前にmixiで一瞬だけマイミクになった方。その方のプロフィールに「上から目線で話してくる方お断りします」って書いてあって、確か猫の話題が切っ掛けでマイミクになって、一回だけその方からメッセージが来て遣り取りしたことあるんですが、その後数日でマイミク切られた。こと。
メッセージの内容が「教えてもらえますか?」的な質問だったので、わたしは知ってることできるだけ丁寧に書いたつもりだった。それで、それにお礼も来ないで切られるという、ね。
今思うと、質問の内容が知りたいんじゃなくて、わたしがどんな表現で答えてよこすのか試されたのかな?と。それで、彼の人の嫌いな「上から目線口調の文章」をわたしが書いている、と判断して、その上でのカットアウト。
そうかあ。それもありなんですか。
そんなの分からなかった。分かってたらこっちから「なんだかなー。」と思ったと思います。
mixiでもどこでもいいんですけど、退会・再入会をそんなに間を置かずに、のケース。
わたしは一回入会登録したら「メインのアカ」はどこも退会した事ないのですが、そうする事情があることがあるのは分かります。そもそも自由です。
その時って、それが目的だったりついでだったり様々でしょうが、人間関係のリセットって、やっぱりしますよね。わたしもそういうことになったらきっとするんじゃないかと思います。これ以上のいい機会ってないと思います。
で、わたしが、その人が新しく選んだ人間関係に入ってなかった時。ほんとにそんなことその人の自由なんですけど、ああやっぱり、と納得する時と、え、なんで?ってショックだった時と、両方ありました。
なんで知るか。わたしの現在繋がりある人が、再び繋がっていると丸見えだからです。
中には「誰と誰が繋がっている」っていうのをシークレットにできるSNSもあるんですが、わたしはそこでも丸見え状態にしています。そこでは自分から切った人もまだいないですね。今まで幸いにして切るほどのことはなんにもなかったので。
だからどうだって言うんじゃないんですけど、ほんとに。そういうことってどうしてもあるんだな、みんなあるんだな、ってかんじですか。
みんなあるからそれがどうだって、それもありますけど。
なにが言いたいのかわからなくなった。ただこれ言いたかったんだと。
メッセージの内容が「教えてもらえますか?」的な質問だったので、わたしは知ってることできるだけ丁寧に書いたつもりだった。それで、それにお礼も来ないで切られるという、ね。
今思うと、質問の内容が知りたいんじゃなくて、わたしがどんな表現で答えてよこすのか試されたのかな?と。それで、彼の人の嫌いな「上から目線口調の文章」をわたしが書いている、と判断して、その上でのカットアウト。
そうかあ。それもありなんですか。
そんなの分からなかった。分かってたらこっちから「なんだかなー。」と思ったと思います。
mixiでもどこでもいいんですけど、退会・再入会をそんなに間を置かずに、のケース。
わたしは一回入会登録したら「メインのアカ」はどこも退会した事ないのですが、そうする事情があることがあるのは分かります。そもそも自由です。
その時って、それが目的だったりついでだったり様々でしょうが、人間関係のリセットって、やっぱりしますよね。わたしもそういうことになったらきっとするんじゃないかと思います。これ以上のいい機会ってないと思います。
で、わたしが、その人が新しく選んだ人間関係に入ってなかった時。ほんとにそんなことその人の自由なんですけど、ああやっぱり、と納得する時と、え、なんで?ってショックだった時と、両方ありました。
なんで知るか。わたしの現在繋がりある人が、再び繋がっていると丸見えだからです。
中には「誰と誰が繋がっている」っていうのをシークレットにできるSNSもあるんですが、わたしはそこでも丸見え状態にしています。そこでは自分から切った人もまだいないですね。今まで幸いにして切るほどのことはなんにもなかったので。
だからどうだって言うんじゃないんですけど、ほんとに。そういうことってどうしてもあるんだな、みんなあるんだな、ってかんじですか。
みんなあるからそれがどうだって、それもありますけど。
なにが言いたいのかわからなくなった。ただこれ言いたかったんだと。
ブログでも何か表現することでもいいのだけど、そこで他人に見て(読んで・聴いて)もらい、それが自分に返ってくることを知れるなら、わたしは両方はいらないですね。まずダイレクト過ぎて耐えられないです。
実はカラオケDAMの「DAM★とも」というのがそういうシステムで、誰が聴いてくれたか、その人が評価(ナイス!)をしてくれたかどうかが動画(録音)1曲分ごとに分かってしまうんです。反映されるのは会員さんだけなんだけどね。
わたしは実際試してみて、そんな情報いらないーってすごく感じた。誰にも評価されないなら誰が聴いたのかなんてわからない方が辛くないし(腹立ったりもしないし)、評価があっても誰が票を投じてくれたのかが分からない方が生々しくなくていいです。
誰が、って分かるシステムなら評価なんてできないほうが摩擦(相手に複雑な感情を抱いたりとか)も少なくていいですね。ただ「ああ来てくれたんだ」って思って、その人がどう思ったかなんて知らなくて、少なくとも評価を「する・しない」の二択って厳しすぎやしませんか、って思う。数字で割り切れるものじゃないから。オーディションの応募者と審査員とか、そういうんじゃないんだしね。
そういうところで自分試しできる人ってすごいと思う。何も感じない(動じない)のか最初から期待しないのか…。わたしには難しかったです。慣れる気もしないです。
実はカラオケDAMの「DAM★とも」というのがそういうシステムで、誰が聴いてくれたか、その人が評価(ナイス!)をしてくれたかどうかが動画(録音)1曲分ごとに分かってしまうんです。反映されるのは会員さんだけなんだけどね。
わたしは実際試してみて、そんな情報いらないーってすごく感じた。誰にも評価されないなら誰が聴いたのかなんてわからない方が辛くないし(腹立ったりもしないし)、評価があっても誰が票を投じてくれたのかが分からない方が生々しくなくていいです。
誰が、って分かるシステムなら評価なんてできないほうが摩擦(相手に複雑な感情を抱いたりとか)も少なくていいですね。ただ「ああ来てくれたんだ」って思って、その人がどう思ったかなんて知らなくて、少なくとも評価を「する・しない」の二択って厳しすぎやしませんか、って思う。数字で割り切れるものじゃないから。オーディションの応募者と審査員とか、そういうんじゃないんだしね。
そういうところで自分試しできる人ってすごいと思う。何も感じない(動じない)のか最初から期待しないのか…。わたしには難しかったです。慣れる気もしないです。
ここで日記を書き始めて、今度の1月1日で満13年…。生まれたばかりの子が中学生になるくらいの歳月が経過してしまったんですね。このまま順調に成人を迎えられるかしら?
で、当時(2004当時)はわたしも「嫌われるのが怖い」って常にビクビクしていたことを思い出しました。だからといって自分が自分でなくなるくらい曲げたり媚びへつらったりということはしなかったけどね(スキルがないからできない)。
なんで「嫌われる=怖い」なのか? よく考えると本当になんで?って思います。
別に、こっちが嫌いな人だったら「お互い嫌い」で決別してさっぱりするし(モヤモヤすることもあるけどね)、好きな人だったとしても「悲しい・さみしい・なにが悪かったのか反省etc」であって、怖いっていうのとはまたちょっと違う気もするし。
そのうちに思い付きました!
嫌いな人に対して、こういうとこが嫌いと文句を言うとか、黙って離れるとかじゃなくて「自分が嫌いな人はイジメないと(困らせないと)気が済まない」という人がいるからだ!ってことです。
そういう経験が…具体的なエピソードを憶えてないんだけど、原体験としてあるんでしょうね、わたしにも。
イジメったって、ちょっとした厭味や嫌がらせ(犯罪級じゃないもの)なら、わたしはしぶといから意外と耐えたり撥ねつけたり、あるいは気が付かなかったり(爆)するけど、生存を脅かすような(気持ちにさせる)ことをしてくる人、やっぱり怖いです。精神的なものであっても。
多分その人にとっては「嫌いなお前が自分の目の前でいい気になっている。そのことで自分を嫌な気分にさせた。だから報復だ!」って思考なのかもしれませんが。
そういう人って周囲には分からないようにヒッソリとでもエグイこと「自分が嫌いな人」に対してやってる…よ…きっと。周囲にばれないように、あるいはいかにも正当な理由みたいなこと言ってそういう空気にして…。
そういうのなにかで見聞きして、わたしの中で「怖い」が植え付けられてしまったんだと思う。
そういう人は「人格障害」だったりするのかな。
とにかく、わたしは当時AD/HD発覚直後だったこともあって「失言女王」をようやく自覚したもので、何が相手の逆鱗に触れる引鉄(ひきがね)になるのか解からないことも怖かったんですね。
その後いろんな苦い思いもして、「お互いに失敗しない人はいない。ちゃんと謝って以後気を付け合う」ことで、関係は維持して行けることを身を持って学びました。それができない人は「その人の問題」だということもね。
だから、もうくっだらない理由とか信念の違いで嫌われることはそこまで怖くなくなりました。それが自分は好きな人だったらやっぱりさみしくはありますけど…。
で、当時(2004当時)はわたしも「嫌われるのが怖い」って常にビクビクしていたことを思い出しました。だからといって自分が自分でなくなるくらい曲げたり媚びへつらったりということはしなかったけどね(スキルがないからできない)。
なんで「嫌われる=怖い」なのか? よく考えると本当になんで?って思います。
別に、こっちが嫌いな人だったら「お互い嫌い」で決別してさっぱりするし(モヤモヤすることもあるけどね)、好きな人だったとしても「悲しい・さみしい・なにが悪かったのか反省etc」であって、怖いっていうのとはまたちょっと違う気もするし。
そのうちに思い付きました!
嫌いな人に対して、こういうとこが嫌いと文句を言うとか、黙って離れるとかじゃなくて「自分が嫌いな人はイジメないと(困らせないと)気が済まない」という人がいるからだ!ってことです。
そういう経験が…具体的なエピソードを憶えてないんだけど、原体験としてあるんでしょうね、わたしにも。
イジメったって、ちょっとした厭味や嫌がらせ(犯罪級じゃないもの)なら、わたしはしぶといから意外と耐えたり撥ねつけたり、あるいは気が付かなかったり(爆)するけど、生存を脅かすような(気持ちにさせる)ことをしてくる人、やっぱり怖いです。精神的なものであっても。
多分その人にとっては「嫌いなお前が自分の目の前でいい気になっている。そのことで自分を嫌な気分にさせた。だから報復だ!」って思考なのかもしれませんが。
そういう人って周囲には分からないようにヒッソリとでもエグイこと「自分が嫌いな人」に対してやってる…よ…きっと。周囲にばれないように、あるいはいかにも正当な理由みたいなこと言ってそういう空気にして…。
そういうのなにかで見聞きして、わたしの中で「怖い」が植え付けられてしまったんだと思う。
そういう人は「人格障害」だったりするのかな。
とにかく、わたしは当時AD/HD発覚直後だったこともあって「失言女王」をようやく自覚したもので、何が相手の逆鱗に触れる引鉄(ひきがね)になるのか解からないことも怖かったんですね。
その後いろんな苦い思いもして、「お互いに失敗しない人はいない。ちゃんと謝って以後気を付け合う」ことで、関係は維持して行けることを身を持って学びました。それができない人は「その人の問題」だということもね。
だから、もうくっだらない理由とか信念の違いで嫌われることはそこまで怖くなくなりました。それが自分は好きな人だったらやっぱりさみしくはありますけど…。
“たまたまひとりでも大丈夫”と思えれば、世間の目なんて気にならない/月読寺・小池龍之介さん(後編)
住職・小池龍之介さんへのインタビュー後編は、さみしさと付き合う方法、世間の偏見に負けないための心得についてです。
『さみしさサヨナラ会議』(宮崎哲弥と共著)という著書もある月読寺住職の小池龍之介さん。前回、“さみしい”という感情は脳内物質による錯覚が引き起こすもので、人間関係では満たすことができないと伺いました。
後編となる今回は、そんな“さみしさ”とうまく付き合う具体的な方法や、「“おひとりさま”はかわいそう」という世間の偏見に負けないための心得を教わりました。
さみしさを埋めようとすると
“心の借金”が増えていくだけ
――そもそも“さみしい”と感じてしまうのは、悪いことなのでしょうか?
何を良い/悪いとするかにもよりますが、仏法的な観点からすると、苦しみが増えるのはよくないこと、苦しみが減るのは好ましいこと、とします。ですから、さみしいと感じると苦しみは増えるので、悪いことだと言えそうですね。
ところが、これにはカラクリがあって、多くの人は自分のしていることが“悪いこと”だとわかると、自己嫌悪や罪悪感が湧いてきて、苦しみが増えてしまうんです。だから、「さみしくなっている自分はダメだ」と自分を責めたり、抜け出そうともがくことで、余計に苦しみが増えてしまっては本末転倒です。
――では、どう対処すればいいのでしょうか?
さみしさは、抜け出そうとするとうまくいかないんです。たとえば、さみしいと感じているとき、私たちは「さみしさの部屋」にいるとしましょう。そこで、“さみしさポイント”10Pを受け取ります。でも、その部屋の中にとどまってじっとしていれば、さみしさはやがて消えてなくなり、10Pは返済できるんですよ。
ところが、となりに「友達に電話する部屋」があると、多くの人はつい安易に移動して「さみしさの部屋」を抜け出そうとします。でも、そうすると10Pは返済されずに借金として残る。しかも、電話が終わるとまたさみしくなって10Pが発生してしまい、さみしさの総量が増えてしまうんです。
――さみしさを埋めるために、別のことをしてはいけないということですか?
さみしさを何か別の手段で紛らわそうとする行為はすべて、「さみしさの部屋」から別の部屋へ移動しただけです。つまり、“さみしさポイント”という借金を返済するために、別のところから借金をしている状態なんです。
特に、電話やメール、SNSといった人とのつながりや恋愛など、人間関係で孤独を紛らわそうとするのはおすすめしません。自分の欠損を満たしてくれる相手を求めると、特別扱いしてもらおうと傲慢な態度を取ったり、過剰に卑屈になって相手に従属しようとしたりと、ろくでもない行動を引き起こしてしまいます。
だから、さみしいときは人に会うべきではないし、新しい出会いも求めてはいけないんです。
さみしさも怒りも、必ず消えていくもの
――では、具体的にはどうすればいいんですか?
何もしないことが大事です。まず、さみしさを感じている自分を、「かわいそうだ」とか「ダメな人間だ」などと一切“評価”しないでください。さみしい自分を、ただ“認めて、受け入れる”だけでいいんです。
ざわざわ、もやもやするような、なんらかの身体感覚に意識を向けて、さみしさに寄り添うイメージを持ってください。
――さみしさに寄り添うとは…?
心の中で、自分自身に声をかけてあげましょう。「さみしいんだね、わかるよ、大丈夫だよ」とか、「じっと待っていればそのうち消えるからね」とか、小さい子どもをなだめるような感じです。
他のことで紛らわすのではなく、さみしさのエネルギーそのものと一緒にいてあげて、消えてなくなるまで待つようにしてください。
――では、寝て忘れちゃうというのもアリですか?
それも「寝て忘れる部屋」という別の部屋に移動して、借金を増やすことと同じになってしまいます。
もし、起きていると何かしたくなってしまうなら、楽な状態でゴロゴロと寝転がって天井の木目を数えたり、公園で空を眺めたりして、さみしさが収まるのを静かに待ってあげましょう。意識のある状態で、さみしさが減っていくのを体感しきることが大事なんです。
――なぜ、“さみしさポイント”の借金は増えてしまうのでしょうか?
前回お話しした通り、“ドーパミン中毒”が原因です。さみしさを別の手段で満たすということは、刺激が入力されることでドーパミンが発生し、脳が快楽を得るということです。ところが、次はもっと強い刺激や快感でないと物足りなくなるため、どんどん耐性ができてしまいます。
昔は手紙や電話くらいしか手段がなかったので刺激自体も弱かったし、ドーパミンが切れても、次の刺激を受け取るまでにそれなりの時間がかかりました。そのため、そこまで重いドーパミン中毒にはならずに済んでいたんです。
ところが現代のSNSは、刺激が入力される頻度や速度、その強度もケタ違いに大きいですよね。不特定多数の人から一度に注目され、圧倒的な承認を得られますが、私たちの脳には刺激が強すぎるんですよ。一度に受け取るドーパミンが多すぎてすぐに飽和してしまい、耐性がついてどんどんさみしくなっていく。借金がものすごいスピードで増えていくということです。
――でも、“さみしさ”には終わりがくる、とは思っていませんでした。
この方法はさみしさに限らず、“怒り”に対しても有効です。「物に当たる部屋」や「怒鳴りちらす部屋」、「怒りを我慢する部屋」に移動してしまうと、“怒りポイント”は返済されないまま借金としてどんどん溜まっていきます。
だから、必ず「怒りの部屋」にとどまって、「そうか、イライラしてるんだね、大変だね」と怒りの感情に寄り添ってあげれば、怒りポイントのゲージは減っていき、そのエネルギーも自然と収まっていきます。安心感が諸行無常であるように、さみしさも怒りもすべては無常で、必ず消えていってしまいますから。
“たまたまひとりでも大丈夫”と思えばいい
――無理して恋愛や結婚をしなくていい、と思っている人でも、周囲からの「ひとりなんてさみしい人だ」という価値観にさらされて、考えがグラついてしまうこともあると思うのですが…。
いまや、ひとりで生きていくこともひとつのスタンダードですから、以前と比べれば「ひとりなんてかわいそう」という視線の圧力はだいぶ弱まっているとは思います。むしろ、圧力をかけてくる人たちに「他人の愛情に頼って依存する価値観でしか生きられないのね」と心の中で見返してやることもできるでしょう。
ただ、味方や仲間がいるとか、“おひとりさま”というグループに所属していることに安心している、という意味では、孤独やさみしさを受け入れているとは言えないでしょうね。
――でも、周りの目がどうしても気になります。
それは、幼い頃に親の視線を自分の中に内面化するクセがついているからです。子どもは、親に同調することで愛情や承認を得て、庇護やお世話をしてもらう戦略を取ってきました。そのせいで大人になってからも、相手や世間の規範を内面化しないと、見捨てられ見放されてしまうんじゃないか、という恐怖が残っているんです。
――自分の身を守るために、周りに同調してしまうんですね。
そういった心の仕組みをわかっていれば、「ひとりってさみしくない?」と言われて心がグラついてしまいそうなときに、「ああ、私は今、この人に嫌われたくないという“さみしさ”を抱えているんだな」と自己分析できるようになるのではないでしょうか。まあ、こうなるとほとんど修行の域ですけどね。
ただ、“おひとりさま”として生きていこうとしている人が、他人から言われて不安になってしまうようでしたら、その人はたぶん強がりで“おひとりさま”を選んでいる可能性があると思うんです。
前の恋愛で痛い目を見たからもう嫌だとか、どうせ他の男もそうに違いないとか、何かしらの強い感情によって孤独を抑え込んでいるのだとすれば、あまりよくない状態だと思います。それは、「強がってやせ我慢する部屋」に移動しているだけですから。
――心から“おひとりさま”であることを受け入れていないと、それも借金を増やしていることになるわけですね。
私たち人間は、そもそも生まれたときから孤独でさみしい存在なんです。恋愛相手であれ、自分の親であれ子どもであれ、ある特定の人間関係に自分のさみしさを預けて解消してもらおうとすると、必ず痛い目に遭います。まずは「さみしいから」という理由で人とつながるのをやめてみましょう。
「さみしい自分はかわいそう」などと評価せず、さみしいという感情にただじっと寄り添い、受け入れることができるようになると、ちょっと大袈裟な言い方ですが、人生が変わります。つまり、人間関係に過剰な期待をしなくなって、精神が自立した状態になります。
――かなり強い心が必要になりそうですね。
だからといって、一生ひとりぼっちになるわけではありません。むしろそういう状態のときに出会い、関わる人とのほうが、強烈に求め合うような刺激はない代わりに、ほどほどに満たされた、安定した人間関係を築けるようになるでしょう。
さみしさとうまく付き合って自立できるようになれば、わざわざ「自分はこの先ずっとひとりで生きていく」と頑なに決めなくてもいいんです。“たまたまひとりでも大丈夫”なだけであって、運良くいい人が現れたら好きになればいいし、結婚してもいい。いなければ、それはそれで「ひとりでもいいや」と思える。そういう精神状態を保っていられるなら、相手がいてもいなくても、どちらでもハッピーなのですよ。
Text/福田フクスケ
■プロフィール
小池龍之介(こいけ・りゅうのすけ)
1978年生まれ、山口県出身。東京大学教養学部卒。2003年、ウェブサイト「家出空間」を立ち上げる。同年、寺院とカフェの機能を兼ね備えた「iede cafe」を展開(〜2007年まで)。現在は、鎌倉にある月読寺の住職として、宗派仏教を超えた立場で自身の修行と一般向けの座禅・瞑想指導を続けている。『考えない練習』(小学館文庫)、『超訳 ブッダの言葉』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『しない生活 煩悩を静める108のお稽古』(幻冬舎新書)など著書多数。
http://sololife.jp/article/1325
さみしさは影のようにいつも寄り添っている…みたいな詩(歌詞?)があった気がしたんだけど、誰だか思い出せない。
そんなことを思い出した。
それから、キリンジの「影の唄」の歌詞も浮かんできて、「Drifter」の“みんな愛の歌に背突かれて 与えるより多く奪ってしまうのだ”というフレーズも。
わたしの中でその時その時の記憶が繋がりそうなんだけど、上手く言えない。
いつだって歌も傍に。
さみしいはあたりまえ
2016年12月3日 人間関係 コメント (4) 一日の最後にいいもの読んだので。
こういうの、ちょっと難しいかもしれないけど、大人になる前に授業で時間を割いてでも教えるべきじゃないのかなって思いました。
おやすみ。
こういうの、ちょっと難しいかもしれないけど、大人になる前に授業で時間を割いてでも教えるべきじゃないのかなって思いました。
無理して恋愛や結婚をしなくてもいい。頭ではそう思っていても、どうしようもなく襲いかかる“さみしい”という感情。
ときに家族との関係や友達付き合いまでも面倒なものにしてしまう“さみしさ”の正体はどんなもので、その対処法はあるのでしょうか?
『考えない練習』『超訳 ブッダの言葉』など数々の著書や、新聞の人生相談でも活躍されている、月読寺住職・小池龍之介さんにお話を伺いました。
人の心はさみしさを
“自転車操業”のように埋めている
――「一人でいるとさみしい」とか、「誰かとつながりたい」といった気持ちは、私たちの心のどういった仕組みで発生するのでしょうか?
足りていないから、なんとか足りるようにしたいと思い悩む欠乏感や欠落感のことを、すべてまとめて“さみしさ”と私は定義しています。
本来、さみしさって人間関係とはまったく関係なく生じるものなんです。
いつも楽しめているものが楽しめないとか、あってほしいと思っているものがないとか、そういうことだけでも“さみしい”という気持ちは生じますからね。
――たしかに、さみしさの原因は人間関係だけとは限りませんね。
ですから、“人とつながる”こと以外でも、さみしさを満たすことは可能です。たとえば、何か足りないという渇望感を抱いたとき、食欲に走る人は多いですよね。性欲もそう。セックスの快楽も一時的には満たしてくれます。
このように、さみしさの代替行為は実はたくさんあるのです。しかし、私たちはそれらよりも、人とつながることで他人から受け入れられたり、重要な存在として扱われたりするほうが、よりレベルの高い永続的な満足が得られると思いがちです。
――俗に“人のぬくもり”と言われるものですね。
そのため、“さみしさ”は人間関係において足りてない状態を指すことが多いんです。だから、多くの人は誰かと会ったり、電話したり、メールしたり、SNSに投稿したり、そういった“人とつながる”ことでさみしさを解消しようとします。
でも、人間関係によって得られる満足も、食欲や性欲と同じで、すぐに消えてしまう一時的・刹那的なものにすぎないんです。
人から愛情や承認を受け取ると、脳内ではドーパミンが分泌されるので、一瞬は満たされます。
ただその快感は長持ちせず、すぐに色あせてしまうので、また満たし直さなければいけないという、すごくあやうい零細企業の経営のように“自転車操業”で回っているんです。
満たされると感じるほど、
余計にさみしくなってしまう
――自転車操業を続けてしまった場合どうなってしまうのでしょう?
快感が切れてしまったあとは、「もっと愛されたい」「もっと受け入れられたい」という、禁断症状が出てきます。
そうやって、刺激(愛情・承認)→快感(満たされた気持ち)→渇望感(やっぱりさみしい)というパターンを繰り返すうちに、脳に耐性がついてしまう。すると、前よりも強い刺激でないと満たされなくなり、より強いさみしさが引き起こされ、結果、常に人とつながっていないと不安になってしまう、というわけです。
人の心は、満たされれば満たされるほど、余計にさみしくなるようにできているんですよ。
――なんとも皮肉なものですね……。では、自分の親や家族、恋人のように、より強い愛情や承認を得られるような相手には、より強いさみしさを感じてしまう、ということですか?
その通りだと思います。私たちは、とりわけ家族やパートナーに対して、過剰な期待を抱きがちです。そして、それが叶わないと他の人よりも強い怒りや、憎しみを抱くので、よりさみしくなります。
特に恋愛は、「愛されたい」「求められたい」という渇望感を強烈に満たしてくれますからね。すると、脳はもっと強い快感を欲しがって、その反動で、より強い「さみしい」「満たされない」という不安を引き起こそうとする。だから人は、恋愛すると不安になりたがるんです。
――特別な期待や要求をしてしまうからこそ、相手にネガティブな感情を抱いてしまいやすいんですね。
私たちは、目の前の相手の言動が原因で怒ったり不安を感じたりしているように錯覚していますが、本当はもともと自分の中に怒りや不安といった“感情のエネルギー”があって、たまたま目の前にいる人をそのターゲットにしているだけなんです。
人は自分の世界の中に閉じこもっていて、そもそもすごく孤独なんですよ。
相手が自分を愛してくれないから、腹を立てたりさみしくなったりしているのではなくて、私たちはそもそもさみしくて、それを満たしてくれるはずだと思い込んでいる相手が満たしてくれないことに勝手に腹を立てている。因果関係が逆なんです。
「自分がさみしいから、相手に腹を立ててしまうんだ」と理解していれば、むやみにイライラしたり不安になったりしても無意味だと気付くはずですよ。それを自覚できている人はほとんどいませんが…。
結婚でさみしさは解消されない
――家族やパートナーに対して、なぜ過剰な期待や要求をしてしまうのでしょうか?
そこに、“特別な絆”や“無償の愛情”があると信じているからでしょうね。
しかし、残念ながら人間関係というのは、多かれ少なかれ「自分がしてあげたから、相手も返してくれる」という交換関係なんです。打算や利害関係が一切なくて、無条件に自我を肯定してもらえる人間関係なんてありません。それは家族やパートナーであっても同じです。
でも多くの人は、自分が何もしなくても特別扱いしてくれる相手、というのを求めてしまうんですね。
――親子やカップルの間には、“特別な絆”や“無償の愛情”が成立しているように見えますが…。
それは、“幸せホルモン”や“愛情ホルモン”と呼ばれるオキシトシンが分泌されるからでしょう。このオキシトシンの分泌によって、相手に対する献身的な愛情が無条件に湧いてきて、相手の欠点が見えなくなります。ところが、やっかいなことに、このオキシトシンの分泌は、長い人でも3年で終わってしまうそうなんです。
“無償の愛”は、刺激が新鮮な間だけ生じる、およそ3年間の幻想なんです。
――それが幻想なら、多くの人は恋愛や結婚なんてしなくなってしまうのでは?
結婚生活は、“特別”だった3年間が終わった後のほうが遥かに長いから、特別な関係なんて幻想だとわかっていて、相手に過剰な期待や要求を抱かない人のほうが、かえって安定したパートナーシップを築けるんですよ。
ところが、得てして「結婚したい」と強く望んでいる人ほど、特別扱いしてくれる相手と結婚すれば一生さみしさから解放されると思っています。だから、3年経ってオキシトシンが切れたとき、さみしさを満たしてくれない相手に失望や怒りを抱くようになってしまう恐れがあります。
――さみしさを動機に結婚するのは、よくないですね…。
結婚でさみしさを解消しようとする人は、その期待が大きすぎるので、満たされずにますますさみしさが増幅してしまう。逆に、結婚に過剰な期待をしていない人は、さみしさを解消したいと思っていないからこそ、結果的にさみしさから解放されることができるんです。
どんな人間関係であっても、一度得られた安心感や充足感が永続するということは絶対にありません。どんな感覚や刺激も、脳の神経に一定の影響を与えたら、やがて必ず薄れて消えていくからです。
でも、消えていくからこそ、また次の感覚や刺激を受け取ることができる。もしも安心感が薄れなかったら、脳がそれ以外考えられなくなり、他に何もできない病気のような状態になってしまいますからね。
――どんな感情も長続きしないのは、脳に必要な機能なんですね。
永続するものなんてどこにもないのですが、だからこそ人はいろんなことに意識を向けて、絶えず変わっていくことができる。それを“諸行無常”と言うんですよ。
(後編に続く)
Text/福田フクスケ
■プロフィール
小池龍之介(こいけ・りゅうのすけ)
1978年生まれ、山口県出身。東京大学教養学部卒。2003年、ウェブサイト「家出空間」を立ち上げる。同年、寺院とカフェの機能を兼ね備えた「iede cafe」を展開(~2007年まで)。現在は、鎌倉にある月読寺の住職として、宗派仏教を超えた立場で自身の修行と一般向けの座禅・瞑想指導を続けている。『考えない練習』(小学館文庫)、『超訳 ブッダの言葉』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『しない生活 煩悩を静める108のお稽古』(幻冬舎新書)など著書多数。
http://sololife.jp/article/1324
おやすみ。
ここしばらく気が付いたら、と言うより知らないふりして意図的に遠ざかっていました。
片想いでもいいから恋愛的な要素が生活にないと死んじゃうー!くらいに依存傾向だったのに、意外と無くても普通に生きられるもんです。でもあったらいいなーと未だに完全には諦めてもいません。でももしもこのまま無くても多分平常心で楽しく生きていける自信はつきました。
今後は「縁を見極められる」ように、諦めず、過度な期待もせず、かな。
もう一通り若い頃の恋愛も結婚も離婚も熟年になるちょっと手前の恋愛もパートナーシップもそれなりにやってきたから、貪欲になろうと思えばまだいくらでもなれるけど、これからは遅かりしのまともな「人間活動」したいです。
これは絶対そうしなきゃ!とか思いつめていませんが、願わくばこれから先、もう一度だんなに対して恋愛できれば嬉しいです。ね。
片想いでもいいから恋愛的な要素が生活にないと死んじゃうー!くらいに依存傾向だったのに、意外と無くても普通に生きられるもんです。でもあったらいいなーと未だに完全には諦めてもいません。でももしもこのまま無くても多分平常心で楽しく生きていける自信はつきました。
今後は「縁を見極められる」ように、諦めず、過度な期待もせず、かな。
もう一通り若い頃の恋愛も結婚も離婚も熟年になるちょっと手前の恋愛もパートナーシップもそれなりにやってきたから、貪欲になろうと思えばまだいくらでもなれるけど、これからは遅かりしのまともな「人間活動」したいです。
これは絶対そうしなきゃ!とか思いつめていませんが、願わくばこれから先、もう一度だんなに対して恋愛できれば嬉しいです。ね。
言葉だけが真実じゃないけど
2015年6月8日 人間関係 言葉が無い、とか、足りない、とか、くどくど言い過ぎる、とか、そういうのが多くなると、気持ちのすれ違いが起こりやすくなってしまうね。
会えないとか、直に顔を見ていないから特に。
何があってもでんと構えていられる強さは全然ない。
言葉で済むなら言葉を大事にしないとね。
会えないとか、直に顔を見ていないから特に。
何があってもでんと構えていられる強さは全然ない。
言葉で済むなら言葉を大事にしないとね。
返事が来なくて、ずっと気にしないように頑張って(こんなことを頑張るって?)、だけどそのうち気持ちが崩れそうになって、そんなタイミングで今返ってきた返信。苦痛が全て融けていくように温まる。
やっぱりあたしはすこぶるさみしがり屋だ。一人でいられるのは好き。だけど独りは嫌い。先に死んでしまいたくない。でも残されるのも悲しい。こんな気持ち、どうしようもないや。
やっぱりあたしはすこぶるさみしがり屋だ。一人でいられるのは好き。だけど独りは嫌い。先に死んでしまいたくない。でも残されるのも悲しい。こんな気持ち、どうしようもないや。
Facebookで疲れる理由は、使い方が間違っているから:研究結果
昨年、「Facebookが私たちを不幸にする」という見出しがあちこちで見られました。多くの人と同じく、あなたも、「あながち間違ってはいない」と思ったことでしょう。当時、ミシガン大学が行った研究で、Facebookを使うほど、そのときの幸福度や、生活全体の満足度が低下することが示されたのです。
しかし、事態はもっと複雑のようです。テキサス大学オースティン校の研究では、正反対の結論が出されました。Facebookを使うと、社会への信頼や参加の感覚が増し、より幸福になるというのです。これは、どういうことでしょうか?
タイムラインを眺めているだけだと孤独になる
Facebookデータサイエンスチームの研究科学者、モイラ・バーク(Moira Burke)氏は、問題はFacebookそのものではなく、その使い方にあると言っています。バーク氏の研究で、ソーシャルメディアへの受け身の参加、つまり、他人のやりとりを観察するだけで、自分は積極的に参加しない態度が、孤独感を増幅させることがわかったそうです。
一方、チャットやメッセージ、投稿へのコメントなど、直接的なコミュニケーションを積極的にとれば、むしろ幸福度は高まることがわかりました。今年のはじめ、前述のミシガン大学の研究者たちがフォローアップの研究を行ったところ、バーク氏と同じような結論に至りました。
友人の投稿に積極的に関わり、自分の生活もシェアするべし
科学的心理学会の年次総会で、ミシガン大学の研究主任で心理学者のイーサン・クロス(Ethan Kross)氏は、Facebookを使うこと自体は幸福にとって害とはならないが、ただ「眺めているだけ」だと害になりうる、と説明しました。同大学の最初の研究では、被験者たちに1日3回、アンケートのメールを送り、感情的な幸福度について答えてもらいました。今回の研究では、被験者を研究室に何度か呼び、それぞれのFacebookアカウントを指示されたやり方で使ってもらい、経過を観察しました。
すぐに明らかになったことは、被験者が写真の共有、ステータスの更新、友人へのメッセージなど、Facebookを積極的に使った場合は、1日を通して感情の変化は見られませんでした。一方、自分は積極的に参加せず、投稿された写真や、ほかの人の会話をただ眺めていただけの人は、ネガティブな気分に陥りました。
ここからわかることは非常にシンプルです。「見ているだけ」の人になってはいけないということです。Facebookから最良のものを引き出すには、友人や家族との会話に積極的に参加し、自分の生活の一部をシェアすることです。
増幅するFacebook上の「ねたみスパイラル」
人は輝かしい瞬間しか、ソーシャルメディアにシェアしないことも覚えておきましょう。Facebookで友人たちの平凡な日常を見ることはあまりないでしょう。その代わり、週末を楽しげに過ごしている写真ばかりを目にするはずです。Facebookにシェアされた情報だけをもとに、友人たちと自分の生活を比べると、自分の生活がみすぼらしく見えてしまいます。
独フンボルト大学とダルムシュタット工科大学の研究によると、「Facebookねたみ」を最も引き起こしやすいのは、休暇旅行の写真なのだそうです。ほかにも、家族の幸福、身体的な魅力などを強調した投稿もねたみの元になります。また、自分よりほかの人のほうが「いいね」や誕生日のメッセージを多くもらっているのを見るのも、ねたみを誘発します。
「Facebookねたみ」を感じた人は、お返しするかのように、Facebookでことさら自慢をする傾向にあります。男性なら、何か成し遂げたことを、女性なら自分の容姿の良さや、社交の華やかさを喧伝します。他人にねたみを感じ、わざと自慢したり、生活を飾り立てる行為をみんながとれば、凄惨な「ねたみスパイラル」が引き起こされます。それぞれが、自分を誰よりもよく見せようとやっきになるのです。
さらに別の2つの研究によると、こうした欲求不満やねたみの感情は、受動的な態度に関連しているのだとか。つまり、Facebookねたみは、自分は積極的に参加せず、ほかの人の投稿をただ見ている場合に起こりやすいということです。
ソーシャルメディアそれ自体は、善でも悪でもありません。重要なのは、それを生産的に使う方法を学ぶことです。ソーシャルメディアを、他人と比べるためではなく、社会生活を広げる手段として使いましょう。
Marianne Stenger(原文/訳:伊藤貴之)
http://www.lifehacker.jp/2014/08/140831facebook.html?cx_click=ranking
朝から地元の天気予報を見る度に(いつの間にか設定直っていてまた表示されるようになっていた)、最高気温が35℃→36℃→37℃、と1℃ずつ更新されていってる。泳ぎに行けたらいいのに。
誰かの重荷になりたい。こいつがいるから自分は死ねない頑張らなきゃいけない、支えてやらなきゃいけない、くらいの存在になりたい。でも、それは長女以外でね。
母親が死んだらそういう人はもういなくなってしまったから、ある一定期間だけでもいいから(ずっとだと本当にお荷物だろうから)、それくらい強く思われたい、と思う。そして思われている人がただ純粋に羨ましい。
今夜はお豆腐に葱2種(青葱白葱)、大葉、おろし生姜をいっぱい乗せて冷や奴にして食べた。美味しかった。それから薄味のにくじゃがを作って食べた。
わたしは実の母の作ってくれた料理をほとんど再現できない。教えてもらったように作っても、どうしても自己流か義母が作ってくれた味に近くなってしまうのだ。
母にごはんを作ってあげたことなんて本当に数えるほどしかなかった。だから仕方ないのだろうか。
子どもの頃は偏食で、母か祖母の作ったもの(その中でも好きな物)しか受け付けられなかった。外食も嫌いだった。余りにも食べないので当然のように痩せていた。
今まで一緒に暮らしてい(る)た人達に作ったごはんは、その人達が気に入る味を考え考え材料や調味料を選んだ。そういうところは自分が無いみたいに。わたしの作るおかずは味が安定しない。それで30年くらいなんとかなってしまった。これからは減塩調味料を使って、どんどん薄味になっていくように思う。
母親が死んだらそういう人はもういなくなってしまったから、ある一定期間だけでもいいから(ずっとだと本当にお荷物だろうから)、それくらい強く思われたい、と思う。そして思われている人がただ純粋に羨ましい。
今夜はお豆腐に葱2種(青葱白葱)、大葉、おろし生姜をいっぱい乗せて冷や奴にして食べた。美味しかった。それから薄味のにくじゃがを作って食べた。
わたしは実の母の作ってくれた料理をほとんど再現できない。教えてもらったように作っても、どうしても自己流か義母が作ってくれた味に近くなってしまうのだ。
母にごはんを作ってあげたことなんて本当に数えるほどしかなかった。だから仕方ないのだろうか。
子どもの頃は偏食で、母か祖母の作ったもの(その中でも好きな物)しか受け付けられなかった。外食も嫌いだった。余りにも食べないので当然のように痩せていた。
今まで一緒に暮らしてい(る)た人達に作ったごはんは、その人達が気に入る味を考え考え材料や調味料を選んだ。そういうところは自分が無いみたいに。わたしの作るおかずは味が安定しない。それで30年くらいなんとかなってしまった。これからは減塩調味料を使って、どんどん薄味になっていくように思う。
discommunication
2014年8月3日 人間関係 あたしがわるいの?
↑の言葉は、(自分では悪かったとは思わないんだけど)あなたは悪く受け取ったのですね。という意味。あなたが「そうだよ。そのとおり」と言えば(思えば)一応相互理解に至ったということになる。でも、大抵「そんなことないよ」とか「わるいのは自分のほうだ」とか言ってそこで話が止まり、気持ちの上では余計ややこしくなることが多い。わたしは素直に「この人は、これ以上話したくないからと言ってるんだ」と受け取ればいいのだろうか。そうすればそれも相互理解になるのだろうか。
mixiで、毎日アプリのリクエストを送ってくるマイミクがひとりだけいる。その人とはアプリ繋がりでマイミクになったので、最初の「よろしくおねがいします」的メッセージ以来、ただのひとことも言葉を交わすことがない、という関係。
わたしはもう全アプリの活動を止めているので、今でもリクエストしてくる人以外は誰もかかわってこない。その人は空気が読めない?わけではなく、わたしが3日も4日もログインしていない時には一旦送ってこなくなったりもする。
毎日リクエストしてくる彼の人のために、もう遊ばないアプリだけど削除しないでおこう、と思っている。
他のアプリ(だけ)ミクに対しては、マイミク解除のタイミングを完全にハズしてしまったな、とやや苦々しく感じているところ。
ああーあと3時間後には仕事行くのか。だるい。なんか今日は眠いしなー。
↑の言葉は、(自分では悪かったとは思わないんだけど)あなたは悪く受け取ったのですね。という意味。あなたが「そうだよ。そのとおり」と言えば(思えば)一応相互理解に至ったということになる。でも、大抵「そんなことないよ」とか「わるいのは自分のほうだ」とか言ってそこで話が止まり、気持ちの上では余計ややこしくなることが多い。わたしは素直に「この人は、これ以上話したくないからと言ってるんだ」と受け取ればいいのだろうか。そうすればそれも相互理解になるのだろうか。
mixiで、毎日アプリのリクエストを送ってくるマイミクがひとりだけいる。その人とはアプリ繋がりでマイミクになったので、最初の「よろしくおねがいします」的メッセージ以来、ただのひとことも言葉を交わすことがない、という関係。
わたしはもう全アプリの活動を止めているので、今でもリクエストしてくる人以外は誰もかかわってこない。その人は空気が読めない?わけではなく、わたしが3日も4日もログインしていない時には一旦送ってこなくなったりもする。
毎日リクエストしてくる彼の人のために、もう遊ばないアプリだけど削除しないでおこう、と思っている。
他のアプリ(だけ)ミクに対しては、マイミク解除のタイミングを完全にハズしてしまったな、とやや苦々しく感じているところ。
ああーあと3時間後には仕事行くのか。だるい。なんか今日は眠いしなー。
わたしはどちらかと言うと言動にデリカシーの無い部類の人間です。極上の?デリカシーを持つ人達を知らずに傷付けてしまっているだろうと思います。黙って許してくれて、ごめんなさい。ありがとう。
急遽明日の夜4時間頼まれることになった。相手は店長(自分の娘)で、訊けばその時間まで寝ないと倒れちゃう! ってくらいハードスケジュールだったので(普段もかなりハードだけどね)、慣れない夜勤だけど代わってあげることにした。
「あげる(た)」とか言うと恩着せがましく思われるかもしれないが、特にそういう意図はない。相手から頼んできたので他に適切な言葉がないのだ。わたしが「…(して)あげる(た)」と書く時はほとんどそんな事情からで、自分では別に上から目線のつもりは毛頭ない。それに別にわたしから是非にと頼んで代わってもらうわけでもないし、こういう日常のことで「…させて戴く」ってへりくだる言い方するのもなんかヘンじゃないかなって感じるしね。口語では「あーそんならわたし代わるね」である。
だいたい恩なんか着せたって返ってこないんだから(恩仇のが多い世の中)、そんな考えは最初から排除してる。相手が誰であれ「できないことはしない。引き受けない」というスタンス。もちろん保証人とか連帯保証人とか絶対無理。「名前を貸す」とは「命を貸す」こと。
閑話休題。
そんなカンジで、今週はほとんど4連休なんだけど最後だけちょっと出勤、になった。夜勤と言ってもいつも起きている時間帯。店長はわたしが不慣れなので、当日夜に納入される商品の発注を抑え目にしておいてくれると言っていた。
今回、わざと矛盾を含ませてみた。根本のホンネは別だってことが分かってしまいますね(爆)。
「あげる(た)」とか言うと恩着せがましく思われるかもしれないが、特にそういう意図はない。相手から頼んできたので他に適切な言葉がないのだ。わたしが「…(して)あげる(た)」と書く時はほとんどそんな事情からで、自分では別に上から目線のつもりは毛頭ない。それに別にわたしから是非にと頼んで代わってもらうわけでもないし、こういう日常のことで「…させて戴く」ってへりくだる言い方するのもなんかヘンじゃないかなって感じるしね。口語では「あーそんならわたし代わるね」である。
だいたい恩なんか着せたって返ってこないんだから(恩仇のが多い世の中)、そんな考えは最初から排除してる。相手が誰であれ「できないことはしない。引き受けない」というスタンス。もちろん保証人とか連帯保証人とか絶対無理。「名前を貸す」とは「命を貸す」こと。
閑話休題。
そんなカンジで、今週はほとんど4連休なんだけど最後だけちょっと出勤、になった。夜勤と言ってもいつも起きている時間帯。店長はわたしが不慣れなので、当日夜に納入される商品の発注を抑え目にしておいてくれると言っていた。
今回、わざと矛盾を含ませてみた。根本のホンネは別だってことが分かってしまいますね(爆)。
平日に3連休しちゃって土曜から4連勤だと、また曜日感覚があやふやになってくる。それでもやっぱりカレンダーが今のところ唯一の拠り所。実感持てなくてもね。
さっき三女が毎月恒例の自分あての封書や請求書を取りに来て、あ、今日って日曜日かーと漠然と思った。
今年の始め、姉妹間のイザコザが発端となって、突然(に思えた。当時は)家を出て行った三女。もう半年以上離れて暮らしているが、会う度に彼女はいつも活気があふれて明るい表情をしている。本人曰く「狭いワンルーム」で好きな人とふたりで暮らしていることが、それは幸せな生活を送っているんだろうなと思わされる。家で一緒に暮らしていた時の彼女を思い出せば、たまに帰って来て愚痴も言わず泣き顔も沈んだ顔も見せないということは、今の生活が真実(ほんとう)に彼女にとって幸せなんだろうと。母としてはそれがなにより。
自分の若かりし頃を振り返れば、DVもモラハラも無関係な、三女を大事なパートナーとして扱ってくれて、それ以前にひとりの人間として認めてくれて、その「狭いワンルーム」で協力し合って仲良く楽しく暮らしていける三女の彼氏は、他のことがどうであれ、精神的にはほぼ年相応に成長してきた(していっている)人だと感じている。わたしが娘だった頃に巡り合えなかったタイプだわ。苦笑。
わたしは付き合うたびに相手からすごい束縛を受けていて、それを当然に思わなきゃ相手に悪いとヘンな我慢を続けてきたからなぁ…。愛情と勘違いしてたし。願わくば三女がそのパターンでは無いことを祈ってしまう(三女はまだ生まれていなかったのでわたしのそういう姿を見せてはいないが)。
三女が家を出て行った時は「うちの家庭事情的に恥ずかしい話」だと思っていたが、今では別にそうでもなくなってきた。感覚が麻痺したのか、結果が良ければそれでいいじゃないと思うようになったのか…。
さっき三女が毎月恒例の自分あての封書や請求書を取りに来て、あ、今日って日曜日かーと漠然と思った。
今年の始め、姉妹間のイザコザが発端となって、突然(に思えた。当時は)家を出て行った三女。もう半年以上離れて暮らしているが、会う度に彼女はいつも活気があふれて明るい表情をしている。本人曰く「狭いワンルーム」で好きな人とふたりで暮らしていることが、それは幸せな生活を送っているんだろうなと思わされる。家で一緒に暮らしていた時の彼女を思い出せば、たまに帰って来て愚痴も言わず泣き顔も沈んだ顔も見せないということは、今の生活が真実(ほんとう)に彼女にとって幸せなんだろうと。母としてはそれがなにより。
自分の若かりし頃を振り返れば、DVもモラハラも無関係な、三女を大事なパートナーとして扱ってくれて、それ以前にひとりの人間として認めてくれて、その「狭いワンルーム」で協力し合って仲良く楽しく暮らしていける三女の彼氏は、他のことがどうであれ、精神的にはほぼ年相応に成長してきた(していっている)人だと感じている。わたしが娘だった頃に巡り合えなかったタイプだわ。苦笑。
わたしは付き合うたびに相手からすごい束縛を受けていて、それを当然に思わなきゃ相手に悪いとヘンな我慢を続けてきたからなぁ…。愛情と勘違いしてたし。願わくば三女がそのパターンでは無いことを祈ってしまう(三女はまだ生まれていなかったのでわたしのそういう姿を見せてはいないが)。
三女が家を出て行った時は「うちの家庭事情的に恥ずかしい話」だと思っていたが、今では別にそうでもなくなってきた。感覚が麻痺したのか、結果が良ければそれでいいじゃないと思うようになったのか…。
うちのお店の店員さん達にはそれぞれのファン(みたいな人)がいて、それは常連のお客さんだったり業者の人だったりまあ様々だけど、わたしには「わたしのファン」がいないなぁと気付いた。もう1年8ヶ月同じお店で同じような時間帯で働いてきたのに、自分にだけいないと分かると最初はなんとなくショックだった(笑)。いや別にそんなことではメゲないけどね。いいことばかりじゃないのも知ってるし(←酸っぱい葡萄的思考キタ―!ですか?)。
自分の気持ちと向き合ってみても矢面に立つより黒子的存在でいたい、というところに落ち着いた。ちゃんと人の役に立っているのならそれがいちばん心が安定するわ。
自分の気持ちと向き合ってみても矢面に立つより黒子的存在でいたい、というところに落ち着いた。ちゃんと人の役に立っているのならそれがいちばん心が安定するわ。
AD/HD女性って…
2014年4月16日 人間関係
はっきり「この人って障害!」って思われる人なんてほとんどいない。単に少し自己管理能力が低い(ハッキリ言うとだらしない)とか、天然のおっちょこちょいとか、マトモな躾を受けてきていないんだろうな(これは一部当たっている場合も)、とか、大胆なくせに心配性とかetc…。要するに本人の性格とか養育環境の問題程度で(それはそれで放置していい話じゃないんだけど)済まされてきて、問題の本質に気付いてもらえることなんてほとんどないと言っていい。
そして、AD/HD女性は大抵の人が普通に恋人ができて普通に結婚もできる。よっぽどの人じゃないと人間的には(特に異性にとっては性的にも?)魅力的というか、素直で憎めない人が多い。若い年頃の娘さんなど特にそうだと思う。
そして、何も考えず主婦になってしまって子どもを持ってしまってから自分自身の「どうしようもできない問題」に気付いて悩み苦しんで医療機関に受診することが多いのだと思う(そこが「自覚のないAD/HD男性」との主な違い)。
そして(そしてばっかりだな;)本質的な「克服」ができるということではなくても、「ひとつひとつの小さな問題」は本人の自覚と努力と周囲のフォローで「ひとつひとつ小さな解決」が可能だ。脳機能の特性は変わらなくても、社会で生きて行くことで「障害」とは言わなくなる。
なるべく(特に感情の面で)迷惑をかけないように自己コントロールしながら自分ができることは助力を惜しまない、そういう心掛けで人と関わって行ければ、家庭でも社会でも幸せに生きることはできるんじゃないかと考える。これは別に「AD/HD者」に限ったことではないけど。
あと、以前は深く考えたことのなかった「こちらがどれだけそういうことを心掛けても実行してもそれが通じない人」に関しては、まだ思案中。相手もまた「見えない障害」を持っている可能性が大。
「さっさと縁を切ってしまえ!」と言うのは簡単だけども……。
そして、AD/HD女性は大抵の人が普通に恋人ができて普通に結婚もできる。よっぽどの人じゃないと人間的には(特に異性にとっては性的にも?)魅力的というか、素直で憎めない人が多い。若い年頃の娘さんなど特にそうだと思う。
そして、何も考えず主婦になってしまって子どもを持ってしまってから自分自身の「どうしようもできない問題」に気付いて悩み苦しんで医療機関に受診することが多いのだと思う(そこが「自覚のないAD/HD男性」との主な違い)。
そして(そしてばっかりだな;)本質的な「克服」ができるということではなくても、「ひとつひとつの小さな問題」は本人の自覚と努力と周囲のフォローで「ひとつひとつ小さな解決」が可能だ。脳機能の特性は変わらなくても、社会で生きて行くことで「障害」とは言わなくなる。
なるべく(特に感情の面で)迷惑をかけないように自己コントロールしながら自分ができることは助力を惜しまない、そういう心掛けで人と関わって行ければ、家庭でも社会でも幸せに生きることはできるんじゃないかと考える。これは別に「AD/HD者」に限ったことではないけど。
あと、以前は深く考えたことのなかった「こちらがどれだけそういうことを心掛けても実行してもそれが通じない人」に関しては、まだ思案中。相手もまた「見えない障害」を持っている可能性が大。
「さっさと縁を切ってしまえ!」と言うのは簡単だけども……。
昨日と違ってOさんと一緒じゃなかったから(わたしも酷いこと言うようになったな;)もやもやせずに気分良く仕事ができた日だった。
Hさん(30代子持ち主婦)と入れ替わりだったんだけど、Hさんの仕事はほぼ完璧で、引き継ぎもちゃんと言葉で言ってくれるので気持ちよくバトンタッチできたし、FFも種類や数をいい感じに作ってキレイに並べてくれたんだな、とひと目見て思ったので、わたしも言葉にして彼女にそのことを伝えた。Hさんとはお互いがプラスに作用するコミュニケーションが難しくない。それこそ彼女の性格と人に対する姿勢の賜物だと感じている。
で、突然話は変わって。
血液型で人を判断するのもどうかと思うけど、わたしの生きてきた40ウン年の経験からざっと導き出すと(家族全員O型の環境で生まれ育った『O型女』から見た場合)、
B型には結構相性が良い人が多い気がする。特別努力をしなくてもお互いを「悪意に取らないで済む」っていうか、節度を保ったうえでの「ざっくばらん」でやっていける感じ。でも気性が激しすぎたり頭の回転が速すぎる人だと付いていけない時も…。
それに、わたしが相手を好いても相手は別にわたしなど眼中にない、ことが多いかも(涙)。
A型は優しい人だと痒いところに手が届く、くらいのフォローをしてくれる。だけどちょっと難しいところがあって「あなたがわたしのストレスの元!」みたいなことを言われたり感じさせられたり、わたしのことを「矯正・強制」させようとする意志を感じとると時々しんどくなる。優しいからと甘え過ぎちゃいけない。
でも基本やりたいようにやらせてくれるかな? その裏には「わたしが我慢すれば…」みたいに思ってそうだけど(ごめんなさい)。
ちなみに家族だとだんな・長女・三女がAO遺伝子を持つA型。
O型は女子とはそこそこ相性が良く、お互いの良いところも欠点も分かり合えるし(わたしも30年来の親友もO型)、一旦信頼し合えばかなり険悪なケンカをしたとしてもタイミングを見てお互い仲直りしようと働きかけ合ったりもする。「もうしょーがないなぁ」とか思いながらやっぱりいないと寂しい何か足りない、という感じ。一度裸になってさらけ出し合いをして、それから段々と気を遣ったり、極端に付かず離れずの距離をキープしつつ良い関係でいようとする感じかな。
家族では二女がわたしと同じO型。母親と母方の祖母も。彼女達は「実の家族にA型が多数いる中のO型」という共通点がある。
わたしはO型の両親を持つ生粋の?O型なので、なんとなく自分だけ違う感じがしてちょっと寂しいかも…。
いちばんダメだな、というか相性が良いと思えないのが実はO型男子だったりする。まずわたしが耐えられないし、男性のほうもわたし(O型)を選ばないような人のが賢いと思う。出来れば女子とは違ってさらけ出し合うような濃密な付き合いをしないほうがいい。わたしが多分ほとんど嫌になるから。
そういうことは一方だけのせいではないので、相手もわたしと同じことを思うだろうことも理解している。
家族だと(元、だけど)父親と弟がO型。
きっと程よく距離を置いて、いい人だな、尊敬できる人だな、くらいに見えている段階にずっといられれば、そのまま悪くならずに済むかと…。
AB型についてはサンプルが少な過ぎてまだ分からない、と言うのが正直なところ。「親しく」付き合った人がいないのです。
↑はあくまでも「わたし(O型女)の経験から現時点で導き出したこと」であって、一般的なことではないと思います。特に「血液型診断」とかは読んでいません。いつか読んでみたいけどね。
Hさん(30代子持ち主婦)と入れ替わりだったんだけど、Hさんの仕事はほぼ完璧で、引き継ぎもちゃんと言葉で言ってくれるので気持ちよくバトンタッチできたし、FFも種類や数をいい感じに作ってキレイに並べてくれたんだな、とひと目見て思ったので、わたしも言葉にして彼女にそのことを伝えた。Hさんとはお互いがプラスに作用するコミュニケーションが難しくない。それこそ彼女の性格と人に対する姿勢の賜物だと感じている。
で、突然話は変わって。
血液型で人を判断するのもどうかと思うけど、わたしの生きてきた40ウン年の経験からざっと導き出すと(家族全員O型の環境で生まれ育った『O型女』から見た場合)、
B型には結構相性が良い人が多い気がする。特別努力をしなくてもお互いを「悪意に取らないで済む」っていうか、節度を保ったうえでの「ざっくばらん」でやっていける感じ。でも気性が激しすぎたり頭の回転が速すぎる人だと付いていけない時も…。
それに、わたしが相手を好いても相手は別にわたしなど眼中にない、ことが多いかも(涙)。
A型は優しい人だと痒いところに手が届く、くらいのフォローをしてくれる。だけどちょっと難しいところがあって「あなたがわたしのストレスの元!」みたいなことを言われたり感じさせられたり、わたしのことを「矯正・強制」させようとする意志を感じとると時々しんどくなる。優しいからと甘え過ぎちゃいけない。
でも基本やりたいようにやらせてくれるかな? その裏には「わたしが我慢すれば…」みたいに思ってそうだけど(ごめんなさい)。
ちなみに家族だとだんな・長女・三女がAO遺伝子を持つA型。
O型は女子とはそこそこ相性が良く、お互いの良いところも欠点も分かり合えるし(わたしも30年来の親友もO型)、一旦信頼し合えばかなり険悪なケンカをしたとしてもタイミングを見てお互い仲直りしようと働きかけ合ったりもする。「もうしょーがないなぁ」とか思いながらやっぱりいないと寂しい何か足りない、という感じ。一度裸になってさらけ出し合いをして、それから段々と気を遣ったり、極端に付かず離れずの距離をキープしつつ良い関係でいようとする感じかな。
家族では二女がわたしと同じO型。母親と母方の祖母も。彼女達は「実の家族にA型が多数いる中のO型」という共通点がある。
わたしはO型の両親を持つ生粋の?O型なので、なんとなく自分だけ違う感じがしてちょっと寂しいかも…。
いちばんダメだな、というか相性が良いと思えないのが実はO型男子だったりする。まずわたしが耐えられないし、男性のほうもわたし(O型)を選ばないような人のが賢いと思う。出来れば女子とは違ってさらけ出し合うような濃密な付き合いをしないほうがいい。わたしが多分ほとんど嫌になるから。
そういうことは一方だけのせいではないので、相手もわたしと同じことを思うだろうことも理解している。
家族だと(元、だけど)父親と弟がO型。
きっと程よく距離を置いて、いい人だな、尊敬できる人だな、くらいに見えている段階にずっといられれば、そのまま悪くならずに済むかと…。
AB型についてはサンプルが少な過ぎてまだ分からない、と言うのが正直なところ。「親しく」付き合った人がいないのです。
↑はあくまでも「わたし(O型女)の経験から現時点で導き出したこと」であって、一般的なことではないと思います。特に「血液型診断」とかは読んでいません。いつか読んでみたいけどね。